稲の倒伏と間断灌水
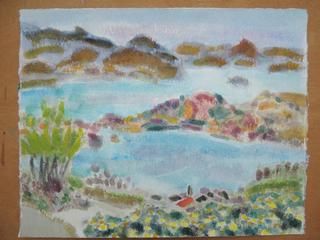
牛窓 10号

4番の苗床後の田んぼ。昨年かなり倒れた。今年もいくらか怪しい兆候が出てきている。
田んぼの写真は欠ノ上田んぼブログに載せています。
アドレス:http://blog.goo.ne.jp/kakinouetannbo
倒伏についてここ数年考えてきた。一昨年のブログの9月に倒伏のことを書いている。そして昨年は思い切って倒れた。倒れながらほぼ畝どりできた。それもあって同じことをぐるぐる考えていたことになる。収量を増やそうとすれば、稲は倒れる。倒伏しないような栽培をすれば、物足りない稲作になる。その為にその境の様なぎりぎりの線を探す栽培に成ってきた。しかし、話では16俵の収量とか、1トンどりとかいうことも聞く。こういうことを普通の品種で可能なものなのだろうか。これを有機栽培でもできるものなのだろうか。等など、色々の考えが頭の中を渦巻いている訳だ。頭だけでなく、試行も続けている。先日、田んぼ巡りの時に、倒伏についてほぐせるような糸口が見えたような気がした。稲の穂は本来もっと小さいものだった、という当たり前のことに行き当たった。収量を増やすために、大きな穂の選抜を繰り返して、現代の品種が出来た。と同時に倒れない為に、背丈の短い品種や、軸のしっかりした品種も改良されてきた。
当たり前のことだが、自然栽培と言いながら、改良に改良を重ねた品種を使っているのだから、倒れるのが普通のことだということに気付いた。倒伏を避ける栽培と言うことになると、自然摂理を少し外さざる得ない。自然ではない人工的農法について考えざる得ないという当たり前のことに気付いた。何でいまさらということだが。
1、根元からばったりと倒れる場合。
ばったりと地面から倒れるのは、田んぼの土壌が緩すぎる場合である。干しを入れない農法のばあい、土の性質でどんどん柔らかく深く成って行く所がある。これは、地下水との関係もある。いずれにしても、耕盤まで緩んでしまうような事がある。田んぼ全体で起こると言うより、一部に起こる場合が多い。緩んでも、稲の根がしっかりと生きていれば倒れることは抑えられる。
2、根元に近い辺りが折れてしまう場合。
根元が折れるのは、茎が弱い場合と早く枯れ上がる場合がある。枯れ上がる場合は、大体に病気で穂も軽いのに倒れることに成る。茎が弱い場合もいくつか原因はあるが、田植えの時に苗を多く植えた場合、茎ががっしりとしない。また、肥料が効きすぎると、根元近くが一気に伸びて、節間が広く成る。節間が伸びると、当然背丈も伸びて、根元に早くから陽が指さなくなる。その為に、ひょろひょろした苗に成る。日蔭の稲の方が背丈が高くなる場合などだ。
3、根元に近い辺りが大きく曲がり、穂が地面についてしまう場合。
これも節間が間延びした生育の場合が多いが、12俵以上の収量に成り、穂が重すぎる場合もある。稲が立派な生育であっても、株間が狭いと、過繁茂に成り倒伏の可能性が高まる。
これが2年前の稲の観察である。ではどういう対策を取るべきかでは、少し考えが変わった。干し以上に、水のかけ引きの重要性である。水の駆け引きが十分にできる土壌と田んぼを作らなければならない。基本的なことだが、田んぼは平らでなければならない。乾かして、しっかりとする土壌でなければならない。そうでなければ干しの効果はない。干しによって田んぼの土を固める事は重要ではあるが、干しは稲の生育には障害ともいえる。これが気付いた点だ。確かにいつまでも水を入れ続けると、倒れやすい柔らかな土壌のままになる。根元の分節が伸びてしまう。伸びれば弱くなるというのも事実だが、順調な生育を遮る様な、分節の狭まりはむしろ穂を小さくする。粒張りも悪くする。後半まで十分な穂への栄養が行くためには、無理な生育の停滞は避けたい。ここに矛盾がある。強い干しでなく、土壌がしっかりとするために、間断灌水と同時に、浅水管理に変えてゆく。苦肉の策である。幼穂形成期ぐらいから、深水から、浅水に変えてゆくこと。
稲の背丈が伸びること自体は悪いことではない。その分がっしりと太い茎を作ればいい。徒長で伸びるのが悪い場合だ。苗を多く植えない。密に植えない。稲藁堆肥をしっかりと作り、田んぼに入れてゆく。冬の緑肥作物を育てることだ。そうした土作りをすれば、がっしりした茎と根が出来る。これが、倒伏をかなり防ぐ効果がある。田植え直後からの深水によって、トロトロ層の厚い形成が促進される。ヒエの発芽が抑制される。雑草対策が深水の主目的であるが、だんだん深くして行くことは、軸のしっかりした稲を作り、過繁茂を避けることになる。中盤以降は雑草は心配がなくなるので、浅くしても、時に田面を出しても、問題がなくなる。こうして水を落とし加減の栽培にする。今年はまだ、完全にこの考えに至っていなかったので、少し中途半端であるが、今のところ間断灌水の成果は出ているようだ。
