小田原ビエンナーレ2025
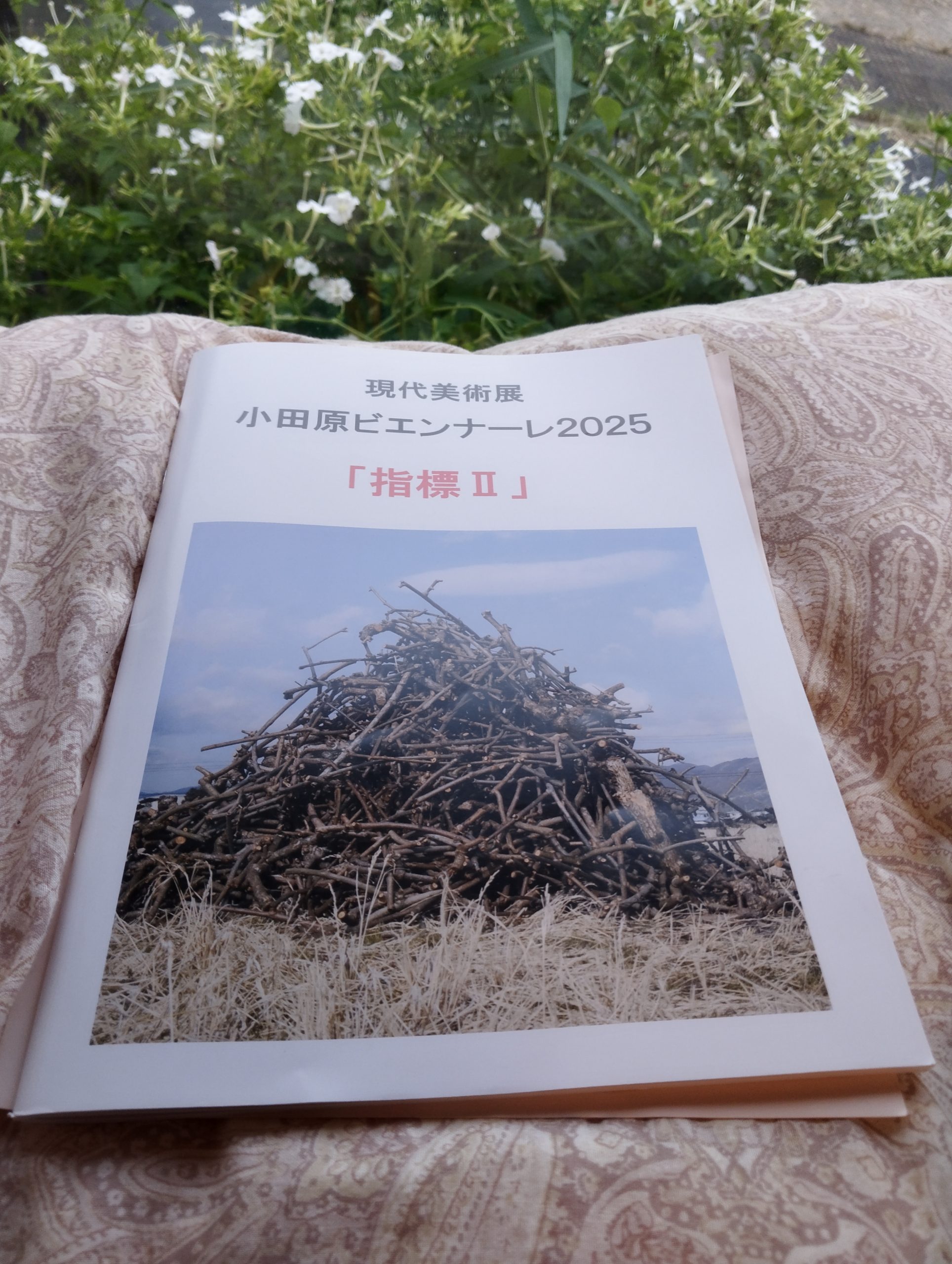
現代美術展 「小田原ビエンナーレ2025」「指標Ⅱ」小田原にある「三の丸ホール」他いくつかのギャラリーで8月25日~9月16日まで開催されている。実行委員会方式で開催されているようだが、石村 実(美術家・美術評論家)の方が企画されているもののようだ。9月7日の午後には講演会が東口図書館で行われるようだ。
秦野に住まわれている、欠ノ上田んぼの仲間である。石原瑞穂氏と石原由紀子氏が参加されている。水彩人の搬入で小田原に来ていて、幸い見ることが出来た。お二人の絵は以前から見せていただいている。本当の絵の友人のお二人だと勝手に思っている。ともかく、お二人の人間が素晴らしい。
おだやかで、したたかで、しなやかで、強い信念の方だ。瑞穂氏の作品はいつもと言って良いくらいテーマは人間の顔である。由紀子氏の作品は光の写実だ。一言で言うのは失礼なことで、まず一応書いただけで、後から今回見せていただいた作品の批評を書いてみたいと思っている。
その前に、会場でいただいた立派な冊子の冒頭に、石村氏の、今の時点で、一九六〇年以降の長い現代美術評論が書かれている。これが読み応えがあり、久しぶりに美術評論を読んだという気になった。評論には関心があり、機会があれば眼に通すようにはしているが、どうも評論はなくなったな。と思っていたので意外だった。
石村実さんという方のことは、知らなかった。1960年生まれで愛知芸大出身の方とある。個展を中心に作品を発表されているようだ。年齢からすると、現代美術の盛り上がった時代のしばらく後の時代の方のようだ。11歳年上の私ですら、現代美術というと、遅れた感じがあった。
今65歳だとすると、現代美術の時代が終わってから、遅れてきたもう一度盛り上がった世代と言うことかもしれない。それにしても文章からすると、むしろ上世代の方かと想像した。多分そういう以前の現代美術が盛んに評論されていた時代のものを、読んだ学んだ方のような気がする。
作家であると同時に、評論家を表明している。こういう方は珍しいのではないか。評論と作品制作をすると、作品の作りが評論家的になる。当然のことだろう。そうでなければおかしい。作品が観念の説明になる。しかし、作品は説明であったら面白くないわけで、評論する脳の動きと、制作する感触とが遊離できるかどうか。
そのことはおいて、よくも小田原ビエンナーレを3回も企画しているものだ。このことには驚く。小田原ビエンナーレのパンフレットの冒頭の文章「すべてのはじまりは、私たちの中にある。」の最後に書かれた文章を写しておく。
私たちの目指すものは、分かりやすい言葉では表現できないもの、モダニズムの理論では語り尽くせないものであるべきです。そしておそらくそれは、私たち一人ひとりの中にすでにあるもので、切実に表現したいと日ごろから願っているもののはずです。(中略)
さらに言えば、私たちの表現の要因は「私たちの中にあるもの」で、それはさまざまな「意味の場」と接していますから、私たちは自由に、そして大胆にそれらの場を移動できるのです。それにそもそも私たちは、日々生成する存在ですから、変化を恐れることはありません。私たちは、あらゆるものが変わっていく中で、その都度懸命に作品を紡ぎ出せばよいのです。
どういう意味だろうか。考えて読んだ。芸術作品はわかりにくいからものであるから、伝わらないものと考えているのかもしれない。作品は明確に意味を語っているはずとしている。確かにそれぞれの作品には観念があり、表現はある。しかし、その表現の内容が、今生きている人の「見る」に届いてはいないと考えている。
石村さんはこうして制作したい作品を誰かが見たいはずだとも書いている。つまり芸術としての、表現としての作品が生きていると考えているようだ。本当に石村さんの作品を見たいと思う人がいると、ここでの「みる」は表現の受け手としてみると言うことのはずだ。難解ではあるとしても、表現が社会側には見る価値のあるものとはいえない、個別的なものになっているのではないか。
絵画芸術がまだ生きていると考えていると言うことなのだろう。社会に影響を与えうる絵画作品があると考えている。果たしてどこにあるのだろうか。石村さんは最後にこう書いている。
あなたの身近にあるもの、例えば「小田原ビエンナーレ」に展示されている作品をよくご覧になってください。あなたにとって、本当に共感できる作品が、きっとあるはずです。そしてその作品との出会いが、新しい時代の「はじまり」を告げているのだと私は思います。なぜなら、「すべてのはじまりは、私たちの中にある」と私は考えているからです。
ずいぶんの楽観である。悪いことではないが。現代美術は芸術表現としての意味失ったという所から、再出発すべきだと思っている。芸術は表現力を失い、社会性がない。その現実にたったときに、制作するものは、作品と自分との関係性を再構築しなければならない。それでも描きたいというものがあり、それは自分と制作の問題であって、社会性はない。
石原瑞穂さんの作品である。制作の中にいる作品だと思った。同時に出されている作品は以前の作品である。現代美術の作品を目指したものだと思う。いわば現代の人間の、存在を掘り下げて掘り下げつくしても、人間に至れない「存在の不確定」。そういう実存の問題が提示されている。
以前はそのテーマを作品の結論として、表現していた。ところが、最近の作品は存在の不確定の感触を制作しながら探っている。いくらたどろうとしても、たどり着けない。カフカの城のようなものだ。見えてはいるが到達できない世界。むしろその城への到達する道をさまよい歩いている様の、描く自分の心情が表現になっている。
明確な結論を描く制作から、むしろ制作そのものが揺らいでいる。つまり、現代美術の成立そのものが、一段深い場所で否定的な感触がある。新しい時代の始まりどころか、一つの時代の終わりに苦しんでいる。絵画の時代の終わりで絵画を探す苦しさ。みる度にその苦しさが深くなっている。
その中で希望と言えば、由紀子さんの保つ空間の美しさの共鳴が起きていることではないだろうか。由紀子さんはものを見て光の織りなす、美的世界の中に永遠の感触というような絶対につながるものを見ようとしている。のではなかろうかと思っていた。みて、真実を感じることが出来るのは、資質なのだろう。筆触が強くなったのかなと少し思ったが、世界は変わらない。変わらない良さというものはある。
絵は自分の世界としての深まりの表現である。見て確かであるものを繰り返し描くと言うことには意味がある。描くという行為に意味が移動してゆく。描いた作品の表現としての他者への意味よりも、自分が見たものを描ききるという行為に意味がある。同じものを繰り返すと言うことは、その意味で正しい制作になる。
もう一段深い世界へ入り込む入り口が、そこからいつ見えるのか。とどうしても期待して見に行くことになる。まあ勝手な見方なのだが。絵には深度がある。その深さの共感のようなものがある。そうなんだその世界はたしかにすごいのだというような共感。勝手な楽しみ方をさせてもらっている。
どうしても私絵画からの視点になる。描く行為の方に目が行く。描かれた絵という結論よりも、どういう気持ちで描いたのかに目が行く。自分の絵からしか人の絵を見ることが出来ない。これも当たり前のことだろう。絵を描く友人としてまた見せてもらいたいと思う。
