水彩人のこれから
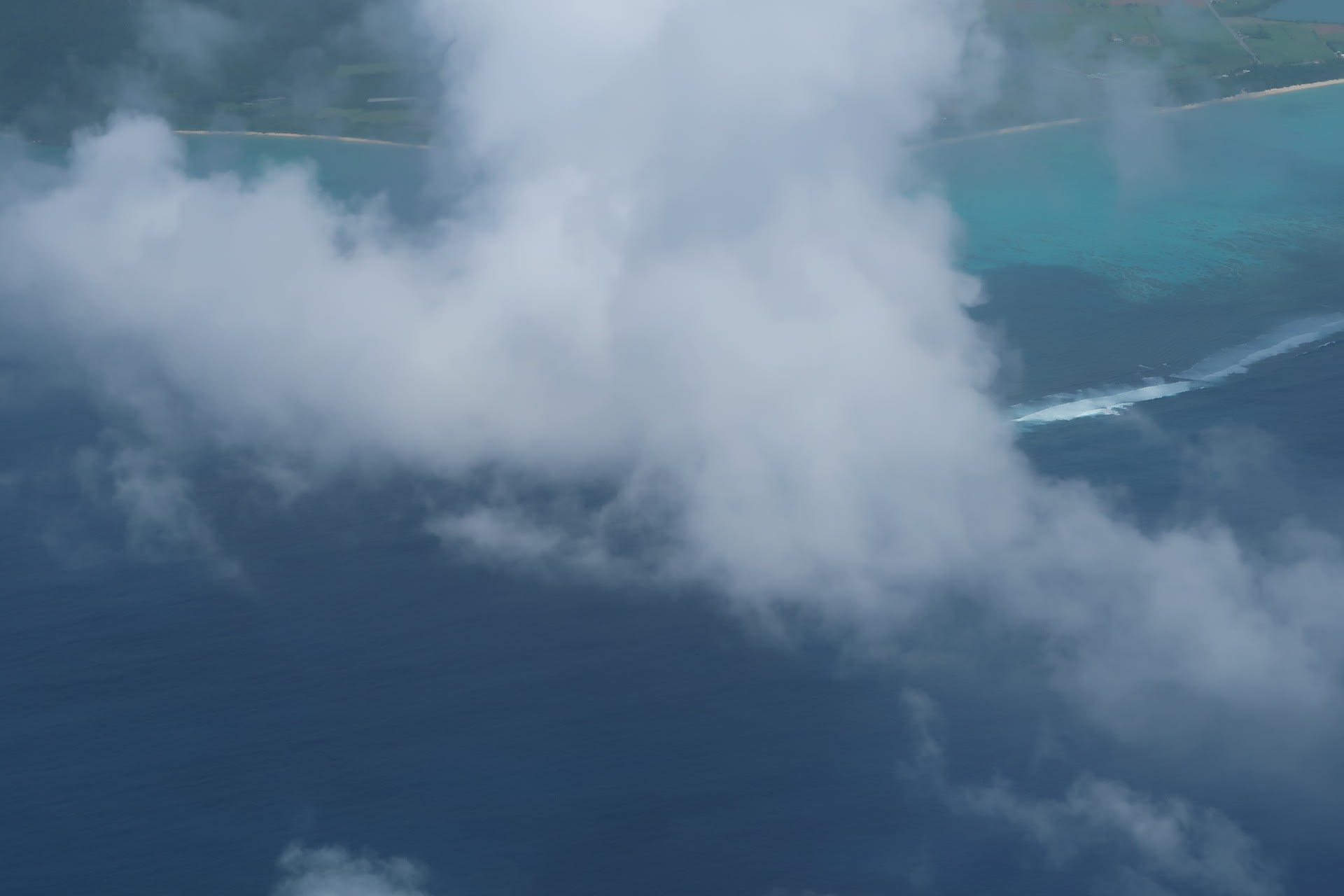
水彩人展は無事終了した。心底良かった。今日これから石垣島に帰る。担当の展示に関しても割合評判は良かった。充実した2週間であった。毎日通ったのだが、特に疲れたという事はなかった。会の絵の内容はまだまだなのだろうが、今やれることは精一杯できたと思う。
まだ正式決定ではないが、次は相模原での展覧会という事になる。良い展覧会になってほしい。水彩人展は年2回の開催が会則で決まっている。何とかどこかで展覧会をやらなければならないということで、相談しながら会場を探した。たまたま昨日までそこで展覧会をしていたという、松田さんがいたので、相模原の市民ギャラリーに問い合わせたなら、6月末に会場が空いているので使えるという事になった。
水彩人では地方展係で、奈良で開催するためにいろいろ進めてきた。奈良の同人に石川のうるわし展の時に相談して、進めてみようとなっていた。いつも地方展を協力してくれる人たちと、代表や事務局に相談して、ほぼいけるだろうという事で進めた。
ところがその場所が奈良でも飛鳥の方なので、やる価値がないという意見の人が現れた。なんで笹村が独断で進めるのだと批判が出た。総会で決められたことではないのだから、総会で了解を経てから進めて欲しいという事だつた。もっともなことなので、奈良展は止めることにした。総会は1月である。そこでの承認を待って進めるとすれば、来年の開催は不可能なので止めるほかない。
水彩人は52名である。展覧会をやるとすれば、かなり広い会場が必要になる。そうした会場の多くは一年前には予約をしなければならない。そうだとすると、2年先の地方展あるいは小品展を上野の本展の機会に打ち合わせをして、おおよそを決めていかなければ開催が難しい。
そして総会までに借りられるめどを立てて提案することになる。しかし、抽選に外れれば、その年は開催が出来ない事にもなる。巡回展を定期的に同じ場所で行っている会は、新しい場所を借りるという事がないので、割合安定して開催して行けるのだろう。
これが正しい進め方だとしても、いったい誰が上手くやれるのだろうかと心配になった。正直、石垣島にいる私が、奈良に行き打ち合わせをして進めるのだから、なかなか調整が難しく、上手く進めることには限界がある。たぶん異論がある中で進めるのでは面倒くさくなってしまうだろう。
できる人がいるとすれば、やはりその地方の人である。福岡県の人が2年先の福岡展を準備して提案するという事なら、可能なのかもしれない。ところが現状地方在住の方からそういう提案が上がらない。これから募集して、2年先の計画を立てたい。
開催したいという提案が上がらないから、そのまま待っているという訳には地方展係としてはいかない。開催に向けて努力してゆく必要がある。地方展の目的は水彩人の水彩画研究の為である。新しい仲間の発掘である。講習会を行い。水彩人の水彩画の在り方を伝えてゆく必要がある。
これは地方展や小品展だけの問題ではない。東京近郊に暮らしている人は、本展の準備に大変な努力をしてくれている。その努力のおかげで、本展は成立している。そのことを考えたならば、地方在住の仲間が、地方展を準備に努力をすべきだろう。今の所それが実現されているのは、金沢のうるわし展だけである。
水彩人の場合、民主主義的運営が会則で決まっている。前出の地方展の話でも、一人でもおかしいという意見が上がれば、やる気がそがれてしまい終わりになる。別段誰にも義務がある訳ではない。会の為と思い努力しているだけのことだから、みんなが喜んでくれるから努力も出来る訳だ。
組織の中にはみんなを黙らせてしまう人がいる。水彩人にもそれなりにそういう人がいる。私ももしかしたらそうかもしれないと思い、書き始めた。簡単に言えば、問題点が良く見える人だ。どのようなことも必ず良いことと悪いことはある。どこまでも比較の問題である。
良い組織は全員がその組織を作り上げている一人であると考えて行動できる組織だ。そうなるためにはその組織が自由で民主的な運営がされていることである。こうした仕組みは大変面倒くさいものだ。独裁組織はその点早い。良いことも早いが、当然悪いことも早い。
なぜ労力をかけて展覧会を開催するのか。それは絵は一人では研究できないと考えているからだ。仲間と一緒に研究して初めて自分の立ち位置が分かるものだ。それは座禅を一人でやってはならないという事と同じだ。独善に至るのだ。そういう人を沢山見てきた。絵は描くだけなら一人で出来るから、おかしなところに落ち込んでしまう絵描きは多い。
公募展に出していれば、いいかと言えばそれもまた違う。今の日本の公募展の絵は、私には大半は絵にはみえない。何なのであろうか。奇妙奇天烈な不思議な絵らしきものだ。ああした絵は展覧会が終われば、廃棄処分する以外方法もないのではないだろうか。公募展向きの絵画と言われるものがあるらしい。
そうした公募展向き絵画の指導塾もあるらしい。私には理解しがたいことだ。各公募展の絵の雑誌が事務所にあったので、じっくり見せてもらった。私が絵だと思えたものは発見できなかった。つまり、私がおかしくなっているか。公募展がおかしいのか。どちらかなのだろう。
その公募展中では唯一水彩人展は絵を描こうという会に見えた。水彩人は下手の集まりだと言われているそうだが、なるほどこういう事なのかと今頃になってわかった。水彩人展は公募展向きの絵画を良しとしていないのだ。私の絵はまさに平凡な風景画である。上手くもないし、特別な特徴もない。自分の世界を探求している絵だ。
多勢に無勢であるが、水彩人に独自性はあると言えるが、下手だと言われればその通りである。そのようになる理由は民主的運営にもある。下手だからダメだとはだれも言わない。水彩人以外に、その様なことを会則で決めた会はないだろう。大抵の公募展は独裁型運営であるのだろう。雑誌に載っている絵が威圧的に見えた。
今回来年6月に「水彩人相模原展」を開催することがほぼ決まった。相模原の駅ビル4階の市民ギャラリーである。ほぼ決まったのは、都美術館での本展で会う人に話して、会えた人すべての人から了解を得たから暫定的に進めていることになる。確かに総会を経なけば決定ではないと言えばそうである。最終決定は1月の総会になる。まあその時に異論が出ても、会場を借りてお金も払っている。どうなるのだろうか。民主主義は難しい。
中判全紙2点を出すことにしたい。場合によっては3点。今度こそよそよそしく無い絵を出したい。内的であり、親密な絵を出した。突き放した絵にしてはダメだと今は思っている。すでに、気持ちは次の展覧会に進んでいる。意欲が湧いているのは、水彩人展のお陰だ。
